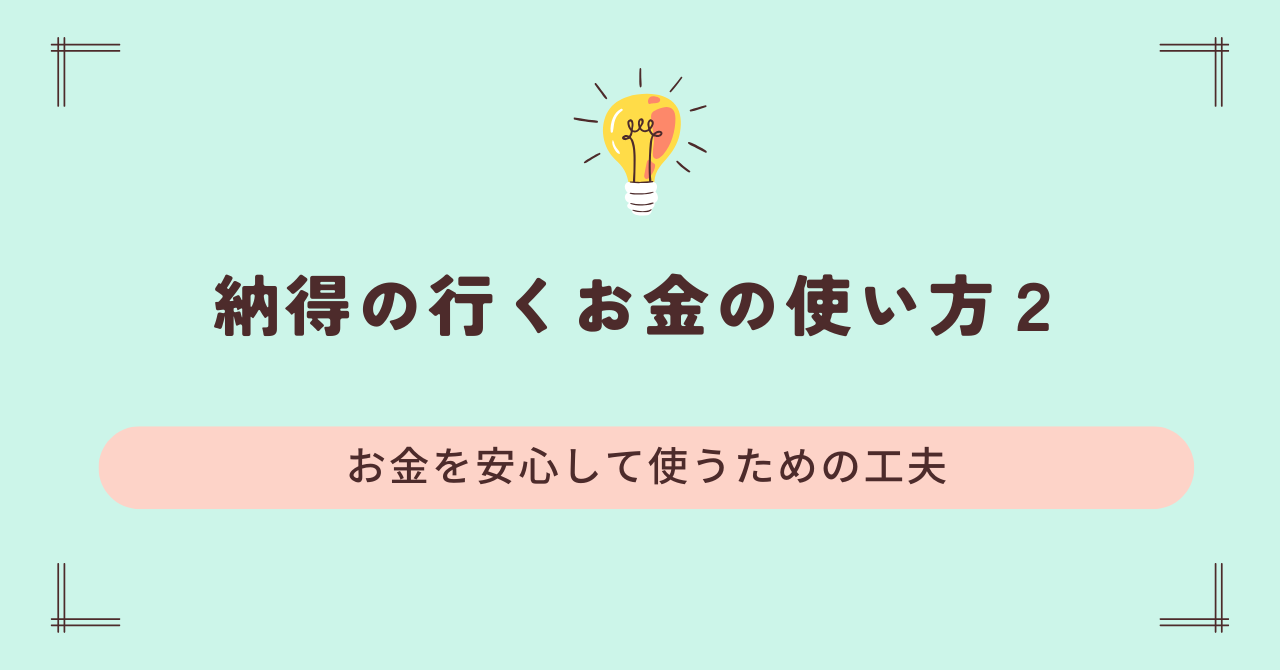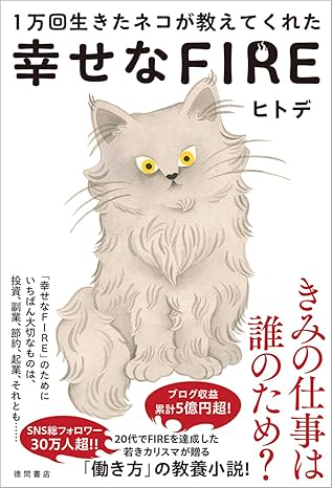セミリタイア実現には、多くのハードルがありますが、「どうお金を使うか?」は、難問です。
働いているうちは、基本的に資産が増えますが、セミリタイア後は、おそらく減少に転じます。
しかし、「減る」とか「使う」ことに対して、まったく慣れていません💦
また、セミリタイアしようとしまいと、年齢的には、「使う」フェーズに移行すべきタイミングです。
本記事では、どうやったら、「納得の行く使い道になりそうか」を考えてみました💡
なぜお金を使いにくいか?
そもそも使い慣れていない
友人や同僚を見ていると、結構、皆、お金を使ってますね。
好きなアーティストのライブだったり、近隣諸国への弾丸ツアーだったり…家族が居れば、1旅行で10万円以上掛かることもザラでしょう。
一方、私は、行っても二泊三日程度の温泉旅行
交通費を入れて、5万円程度が関の山♨
それでも、「ああ、豪遊したなぁ🍺🍖」と思うわけです(カイジのように猛省はしませんが)。
「株は高くても買えるのに、現実のモノは、少額でも躊躇してしまう」というのは「投資家あるある」ですが、まさにそれ。
少し前までは、「仕事で忙しいから、仕方ない」と思っていたのですが、よく考えたら、時間があっても、使わなそう💦
このままでは、セミリタイアしても、何ら変わらない気がしてきました。
資産が減るのが怖い
給与という定期収入がある今でさえ、そんな状態ですから、セミリタイアしたら、どうなるかは自明…💦
特に、セミリタイア生活が軌道に乗るまでの間は、倹約意識が高まりそうです。
これまでの習慣(というかクセ)により、「羽目を外すのが怖い」という面もあるのかもしれませんね。
試算した限り、ある程度は使っても大丈夫なはずですが、非常に抵抗感を覚えます。
「使ってナンボ」は分かっているが…
正直、「お金を使うことが楽しい」と感じたことは、今までのところ、ほぼないです。
初任給は、親に何かプレゼントした気がしますが、「自分にご褒美」的なことはしませんでした🎁
最近は、ボーナスも株に注ぎ込んでおり、「自分のために使う」ということは、全くしていません。
「それは貧しい生き方だ」と思われるかもしれませんが、当の本人は、全然窮屈さを感じていないのです。
もちろん、セミリタイアしたら、もう少し「人生を楽しむこと」に使っていきたいと思っています。
しかし、前述のとおり、「お金を使う=楽しい」という図式がないため、何に使えばよいのか、よく分かりません。
「お金は、使ってこそ価値がある」ということも、頭では分かっているのですが、気持ちが付いてこない感じ…💦

先に対する不安が強く、計画を逸脱することに怖さを感じるタイプなので、より慎重になりやすいのかもしれませんね。
カイジのように、後先考えず、パーッと使える人が羨ましいです(でも、セミリタイアからは、最も遠い存在…)。
浪費することが怖い
一度贅沢を知ってしまうと、それが「標準」になってしまわないか?
ひいては、使い過ぎて資産が減ってしまわないか?という怖さがあります。
また、贅沢に慣れてしまうと、「ありがたみが減ってしまいそう」という不安もあるかもしれません。
優待をもらうようになって、飲食系は、安く利用できるようになりましたが、未だに店で食べると、「贅沢しているなぁ」って気になるんですよね。
こんな「根っからの貧乏性」なので、「贅沢に慣れて使い過ぎる」という可能性は低い気もしますw
むしろ、ちょっと使っただけで、すぐに財布のヒモを締めそうな…(^-^;
お金から、きちんと価値を引き出せているか、心配
これも結構、可能性としては高い気がします。
もともと「節約大好き人間」でしたが、投資を始めてから、一層、「価値ある使い道なのか」考えるようになりました。
特に、投資と比較して、「株を買えば、もっと資産増えるよな…(=セミリタイア生活が充実しそう)」とか考えだすと、それ以上に有意義な使い道が思い付かないため、すぐにブレーキを踏んでしまいます。
投資以外に、「お金から十分な価値を引き出す方法がない」ということですね。
せっかく使っても、あまり有意義と感じられなければ、「なら、株を買っておけばよかった」と後悔しそうで、大胆に使うことが難しくなっているように思います💦
その点、優待は本当に良いです🌟
用途や期限が指定されているので、嫌でも「使う方」に意識が向きます。
同時に、消費意欲も満たしてくれるため、無駄使いが減ります。
小括
こうして振り替えてみると、お金を使えない理由は、「資産が減る不安」「浪費への恐れ」「価値を引き出せない懸念」など、感情と習慣が複雑に絡み合っていますね💦
投資や節約で培った思考は大きな武器ですが、その反面、「お金を使う=不安」という回路も強化してしまいました。
ケチから、ドケチへ進化(退化?)したと言ってよいでしょうww
セミリタイア後、納得して使えるようになるためには、この心理的ハードルを理解し、意識的に乗り越えていく必要があります。
次回は、そのために今からできる具体的な対策を整理します。