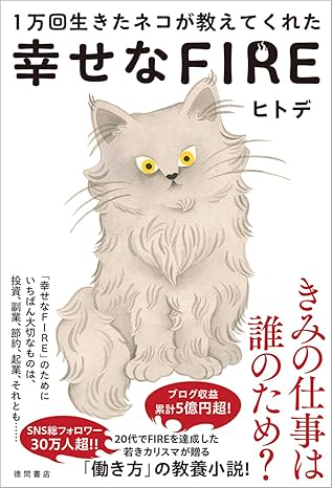※この記事では「安楽死」の倫理的是非を論じるものではなく、「人生の節目における主体的な決断」という観点に限定して述べています。
「セミリタイアと安楽死」
一見無関係に思えるこの2つ。実は意外な共通点がありました
例えば、事故などで植物状態などになったら、周りに負担を掛けてまで、生きたいとは思わない気がします。
また、年を重ね、徐々に身体が動かなくなっていき、できることも、楽しみも減っていったら…
その時、「このまま寿命が尽きるまで、生きていたいのか」、それとも「自分の意思が残っているうちに、死を選ぶのか」、おそらく迷うでしょう(倫理的な問題はさておき)。

この迷いは、セミリタイアする時の迷いに、近い気がしますね。
「メメント・モリ(死を想え)」という言葉の通り、「終わりを意識すること」は、今を輝かせてくれます。
 うさ
うさHunter×Hunterが終わるまでは、生きていたい!
安楽死について考えてみることは、セミリタイアのハードルを下げる(または、上げる)ことにつながるかもしれないと思って、考えてみました。
類似点
一つの人生を終わらせる行為
「職業人としての人生か」、「生命体としての人生か」の違いだけで、人生を終わらせる行為という点は一緒です。
セミリタイアは、「社会人人生を、自分の意思で、早めに終わらせる」のですから、「自決」以外の何物でもありません。
その分、重く、迷い、後悔しないよう、慎重になりますね。
自分で決断する行為
事故死や倒産のように、外的要因によって、突然、終わるのとは違い、「主体的に、自分で選択する行為」という点も、共通しています。
自分の決断なので、責任転嫁することはできず、全て自己責任になります。
その分、とても怖いです。だからこそ、慎重になるわけですね。
「自分で選ぶ自由がある」とも言えます。
安楽死の場合、死後の世界をどう捉えるかは別として、基本的に「死んだら全部おしまい」ですし、「だからこそ、救いがある(リセットできる)」という考えもできます。
一方、セミリタイアの場合は、まだ意識が残っていて、自分の決断を振り返ることができるため、好悪両面ありそうです。
不可逆の行為
「実行したら、後戻りできない」という点も共通です。
出戻りを認めてくれる会社もあるようですが、私の場合はムリ
現職を辞めたら、二度と、同じ待遇では戻れません。
しかし、このまま放っておいたら、ジリ貧になるは必至…💦
だからこそ、大いに迷うわけですね。
時間が経ったら、結局、同じ状態になる(ゴールは一緒)
「放っておいたら、自発的に選択しなくても、同じところに辿り着く」という点も共通です。
セミリタイアしなくても、いずれリタイアしますし、自ら死を選ばなくても、必ず死にます。
結局、ゴールは同じで、そこに至ることは避けられません。
そう考えると、セミリタイアするか否かは、単に「遅いか早いか」の違いだけかもしれませんね。
そして、セミリタイア期間は、人生のちょっとした「寄り道」というか、本来は行けない「ボーナスステージ」のようなもの。
そう考えると、とても貴重な気がしてきます💎
現状に対する「諦め」がある
現職にもメリットはあるけれど、ツラいことの方が多く、働き続けるのはムリそう…💦
死にたくはないが、体調は悪いし、動けないから希望も持てない。生きていてもなぁ…💦
実行できるのは、このように「メリット<<<デメリット」な状態が続いて、「もう、既存のメリットを手放してもいいや!」と諦めの気持ちに至った時でしょうね。
背景にあるのは、「もうラクになりたい」という気持ち
実行するには、現状への未練や、将来への期待を手放す必要がありそうです。
別の道へ進むことを、あえて(自発的に)選択する行為
リスクや先の見えない不安はありながら、あえて、別の世界へ飛び込む行為
つまり、「現状の安定を捨てる行為」とも言えますね。
惰性とは怖いもので、どれだけ「明るい未来が待っている」と言われても、逆に、どれだけ現状がツラくても、なかなか「安定した今」を手放すのは難しい。
ふるさと納税など、メリットしかないことでも、「面倒くさい」「なんか胡散臭い」と言い訳して、結局、始めない人が多いそう(うちの親もそうでした)。
私自身も、「転職活動だけでもしてみよう!」「転職するかは別として、転職活動だけならメリットしかない」と聞いても、ずっと動き出さなかったですから、人のことは言えません💦
結局、人間は、「面倒」「そんなことをする時間がない」「現状よりも悪化したらどうしよう」などと言い訳して、自然と、現状維持を選びやすいものなんでしょう。
進むも地獄、戻るも地獄とすれば、「二の足を踏み続ける」というのも、分かる気がします。
また、セミリタイアも安楽死も、現状においては、いずれも異端というか、一般的なルートではありません。
皆、同じような選択をするなら、諦めもつきますが、そうではないため、失敗すると、「通常ルート」と比較して、後悔しやすい気がします。
そんな中で、決断を下すのは、とても勇気が要ります。
「えいや!」で決断する
どれだけ準備やシミュレーションをして、成功確率を上げても、未来は未定。
不安は完全には拭えません。
そうした不安を振り切って、大きな決断をするには、勇気だけでなく、「思い切り」も必要
というか、思い切らないとムリです💦
人間弱いもので、「一定の資産額になったら」「来年の春まで」などと区切りを設定するものの、いざ、その目標が近付くと、新たな不安が出てきて、簡単にゴールポストを後ろに下げてしまいます。
私も、この春に転勤した当初は、「これでは1年持たないな」と思って、セミリタイア計画を前倒しにしたのですが、慣れてくるにつれ、徐々に、「当初の3年計画に戻そうか…」などと、迷いが生じています。
誰かに迷惑をかける訳ではないし、自分一人のことなので、いくらでも迷って良いのですが、やはり、人間は気まぐれで、不安定な生き物なんだなぁと、しみじみ…
結局、心の準備には、それなりの時間が掛かるということなんでしょう。
外的要因も必要
セミリタイアについては、「精神的に限界を迎えた」「納得の行かない部署異動や転勤を命じられて、組織に愛想が尽きた」「最悪の上司がいて、一刻も早く決別したい」といった外的要因により、決断せざるを得なくなった方も多いですね。
また、「早期退職の募集があった」「保有銘柄が爆謄して、一気に資産が増えた」といった好条件をきっかけに、踏み切るケースも目にします。
もちろん、そうした外的要因に加え、資産などの準備が整っていることが前提条件になるでしょう。
「啐啄同時」と言いますか、資産、リタイア計画、メンタルなど、個人の条件が整ったところへ、最後の一押しとなる外的要因があって、決断するという流れが多い気がします。
やはり、自分一人の力だけで、扉をこじ開けて、羽ばたいていくのはハードルが高いので、背中を押してくれる何かがあった方が、心理的にはラクになりそう。
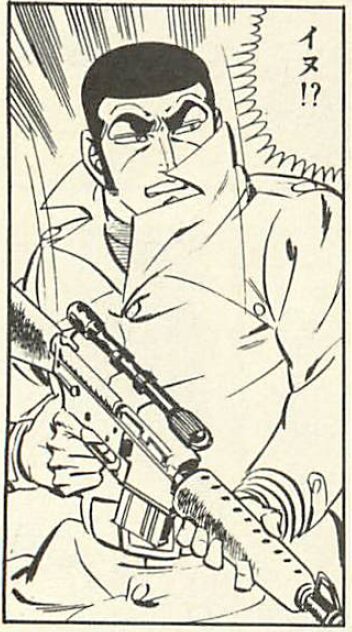
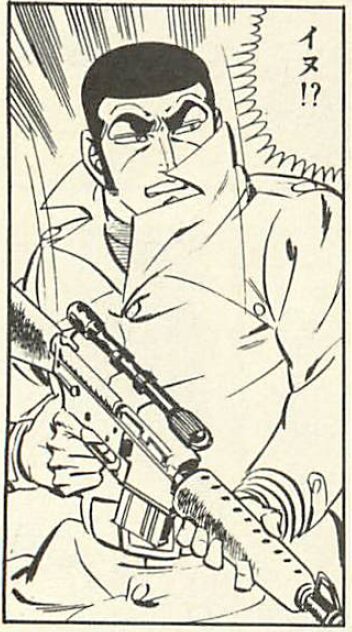
私の場合も、きっかけになりそうな区切りや節目はあります。
今後も、色々と出てくるでしょう。
そのうちのどれを採用するのかは、おそらく「自分で決める」というよりも、その時の状況次第になりそうです。
裏を返すと、きっかけがあっても実行できないなら、まだ「何か(資産、プラン、マインド、覚悟、思い切りなど)が足りない」ということなのかもしれません。
いざ、その時が来たら、きちんと「前に」踏み出せるよう、資産面も精神面も整理しておく必要がありますね🐾
まとめ
セミリタイアは、未来志向
こうして比較してみると、共通点が多い反面、やはり相違点もありますね。
「その後も人生が続いていく」とか「セミリタイアは、ボーナスステージ」という点です。
特に、後者の発想は、とてもしっくり来ました。
セミリタイアは、人生を充実させるため、また、後悔のない人生を送るためにする、前向きな行為です。
現状に対する悲観的な気持ちが端緒であっても、また、救いを見出すような形であっても、セミリタイア後の生活は、現状よりは良いものを期待しているはず。
少なくとも、私にとってセミリタイアは、単なる諦めや厭世観だけで実行するものではない、と感じました。
セミリタイアは「逃げ」ではなく「選び取る自由」
多くの人が無意識に走らされているレールから、一度立ち止まり、自分の人生の方向を“自分で”決めるという選択。
それこそが、本来の意味での「生の自由」なのかもしれません。
死へのリハーサルになる
セミリタイアを考える中で、自分の「理想的な生き方」や「納得の行く人生の幕引き」などを考えるため、自然と、死に対する心の準備ができそうです。
つまり、「セミリタイア=前向きな死生観を養うリハーサル」とも言えるかもしれませんね。
そして、自分が望むような人生を歩めたら、「諦め」ではなく、「納得」して終わりを迎えられるかもしれません。


セミリタイアし、いったん(職業人としての)人生を終えてみて、そこからどう自分の価値観が変化するのか、楽しみながら見ていきたいと思っています。
なんだか、まとまらなくなってしまった
父や祖母の最期を見ていると、やはり辛いことが多いようでした。
好きなものは食べられず、行きたい場所にも行けず、寝たきり
身体のあちこちに不調があって、痛みや苦痛が付きまとう
他人に世話してもらわねばならず、人間としての尊厳も低下していく…
そうなれば、この世への未練が減退していくのも、当然でしょう。
そうやって、少しずつ旅立つ準備をしていくのかもしれませんね。
事実、二人とも、「もう、この世に居なくてもいいな」と思っているように見えました。
(傍観者がそう思うだけであって、本人は、そのような状態であっても、もっと生きたかったのかもしれませんが)
身内としては、当然、少しでも長く、生きてくれることを願っていました。
一方、つらそうな様子を見るたびに、「少しでもラクにしてあげたい」という気持ちが沸き上がり、死が、苦痛から解放してあげる、唯一の手段であることも、分かりました。
「ここから回復したり、良い方へ向かうことはない」という厳しい現実を前にして、どうしてあげることもできない無力感のようなものを感じましたね。
と同時に、「誰もが、いずれこの道を通るのだ」という事実に、愕然としたことを思い出します。
本人も周りも納得して、「もういいよね。」という気持ちで、自然と旅立つ。
自分から決断することなく、自然に命が尽きるのに任せる。
そういう生き方も、また一つだと思います(というか、一般的なんでしょう)。
セミリタイアは、こういった在り方とは趣を異にしますね。
ただ、二人とも、昭和以前の生まれのため、一般的な価値観も、現代とは少し違うかもしれません。
現代は、多様な選択肢があり、また、選択後の結果(=色々な生き方)をSNSなどで知ることができるため、「ベターな選択を選ばないと損」という発想に陥りやすい気がします。
選択肢があるのは良いことですが、その分、「迷う機会」も増えますね。
そうした時代においては、「自分が本当に望むものは、何なのか」を、自分自身に繰り返し問うてみて、自分で答えを出さなければなりません。
より難しい時代になっていると感じますが、こんなことをウダウダ考えていられるのは、有難いことです。
「生きて、自由に動ける」という現状に、感謝することを忘れてはなりません。
私たちは、どう生きるか?
人生の選択に、唯一の正解はありません。
そのような中、「自分で選ぶ」という姿勢こそが、自分を大切にする第一歩なのかもしれません。
なんにせよ、最後は、色々なことに「感謝」して、この世を去りたいですね。
そのために、気持ちに余裕を持った状態で、多くのことを経験し、「有難い」と感じる時間を増やしたいです。
皆さんなら、セミリタイアのきっかけを何に求めますか?