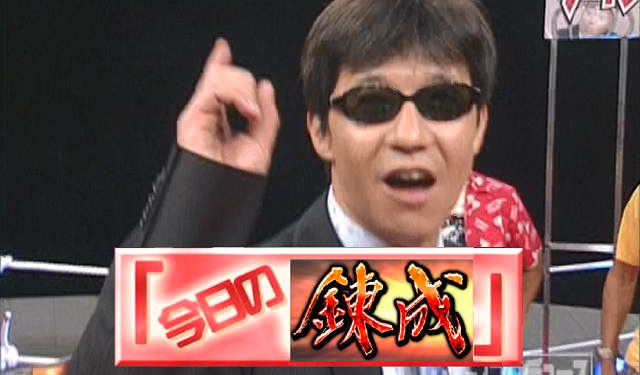今週末(12/19)は、いよいよ2021年度宅建試験の第2回ですね。
受験される方は、最後の追い込みに奮起されていることと思います。
私の受験体験記も、これがラスト。
最後は、試験本番から合格までをまとめます。
当日の準備や心構えなども書きましたので、ご参考になれば幸いです。
試験本番(10/17) ~長い長い一日~
当日の天気は薄曇り。
10月にしては気温が低かったので、ヒートテックにパーカーという動きやすい服装にしました。
受験票に、自宅での検温結果を書く欄があるので、要注意です。
私は、当日もワクチンの副反応で、身体がだるかったので、ひやひやしました。
最寄りの会場が取れなかったので、電車で移動。
早めに着くつもりが、電車の遅延でギリギリに。
下調べをしていた中華料理屋で、昼食のワンタンメンを急いで食べ、何とか会場入り。
個人経営の人気店みたいで、料理の提供が遅く、間に合うかドキドキしました。
当日、慌てると、落ち着いて受験できませんから、馴染みのチェーン店にするとか、おにぎりなどを持ち込んだ方が無難かもしれません。
試験開始は13時からですが、会場への入室は12時30分まででした。
会場スタッフの方は、皆、いかにも不動産関係といった感じ(なぜかガタイもいい)。
笑顔で迎えてくださったので、少し安心できました。
また、隣の方が、若い女性だったので、試験中の騒音などに悩まされる必要はなさそうで、一安心。
一方、机が狭く、椅子の高さと合っていないため(大学のように、椅子が固定式)、かなり疲れそうだなと思いました。
副反応による体調不良が続いていたので、直前にドリンク剤を飲んで、開始の合図を待ちます。
途中、お手洗いには行けないみたいなので、きちんと済ませておくことも大切です。
開始直前は、「これで半年の苦労が無に帰すかも」と思うと、さすがに緊張しましたが、ゆっくり呼吸をするなど、普段のリラックス法で乗り切ります。
試験にあまり慣れていない方は、アロマや音楽など、自分なりのリラックス法を見つけておくのがよいと思います(いずれも、周りの迷惑にならない範囲・方法で)。
そうした方法を、実際に使うかどうかは別として、「その気になれば、自分の意志で、落ち着くことができる」という安心感の方が重要です。
会場に着くまでは、まとめノートなど見て、最終確認をしたのですが、入室後は全く頭に入ってこないので、見るのをやめ、周りを見渡したりして、雰囲気を確認しました。
自分緊張しているかは、意外と気付きにくいものです。
足元がフワフワしたり、何となく落ち着かなかったりと、サインは人それぞれですが、視野が狭くなっていると、見落としが多くなるので、軽くストレッチ(特に、座りっぱなしなので、足回り)をしたり、深呼吸したりして、コンディション作りに努めた方が、実力を発揮しやすいと思います。
また、周りの人が知らない参考書(大抵とんでもなく分厚い)を使っていたり、直前まで勉強していたりすると、急に不安になったりしますが、気にする必要はありません。
周りの方も不安で、じっとしていられないだけのことが多いです。
実際、私の受験会場は、200人ほど受験者がいたようですが、合格したのは30人足らずでした。
スマホやタブレットPCは、用意された封筒に入れて、机の下に入れておくよう指示があります。途中で鳴ったりすると、失格になる可能性もあるので、電源OFFも忘れずに。
開始の合図とともに、まずは、乱丁・落丁の有無や解答用紙のスタイル、全体の感じを軽くチェック。
苦手な計算問題(建ぺい率や容積率)はなさそうで、一安心しました。
周りの音を聞く限り、いきなり解き始めている方が多かったですね。
私は、全体像を把握した方が安心できますし、視野を広く持てるので、必ず試験開始時は、このようにしています。
1分程度で済みますし、慌てて始めてミスをする方が痛いので。
模擬試験と同じように、問1の①権利関係から解き始めましたが、「解きやすい宅建業法などから始めた方がよい」という意見もあるようですね。
確かに、最初は緊張モードにあって、頭がうまく働かないため、問題文が平易な宅建業法や統計問題から始めた方がいいというのも、分かります。
スタートダッシュが掛けやすい、しり上がりに調子を上げていけるといった、自分のタイプに合わせて決めるとよいでしょう。
ただし、いきなり本番でやり方を変えない方が良いと思います。
あとは順番に、無我夢中で、進めていきました。
途中、自信が持てない問題が続くと、ものすごく不安になりますが、何とか終わりまでたどり着きました。
解答方法については、「1問ごとにマークする」、「全部解いた後で、まとめてマークする」など、色々あると思います。
私は、模擬試験の様子から、ある程度、時間は余るだろうと予想していたため、一問ごとにマークして、あとで全体を見直す形にしました。
模擬試験で、解答用紙の書式(縦に解答するのか、横に解答するのかなど)に馴染んでいた点は、よかったと思います。
なお、今年は、LECの模擬試験のとおり、上から下へ、2列に25問ずつ回答するようになっていましたが、今後、変わる可能性もゼロではないので、その都度、確認した方が良いと思います。
そのためには、模擬試験の段階から、解答用紙を確認することを習慣化しておくとよいと思います。
私は、50問解くのに70分掛かりました。
解き切れた安堵感と、ドリンク剤の効力切れで、かなり疲弊していましたが、「見直しは必須!」と、気力を振り絞ります。
見直しについては、問題文が短い法令上の制限(問15)から始め、時間があれば、権利関係(問1~14)に戻ることにしました。
悩んだ末に、結局、2問ほど回答を変えましたが、一勝一敗でした。
すべての見直しも終わり、自己採点用として、問題用紙に自分の回答を書いて終了。
なんだかんだで、見直しを入れると、時間ギリギリでした。
終了後も、しばらくの間は、解答用紙の回収などに時間が掛かります。
緊張の中、2時間も集中すると、疲労感は相当出ますので、忘れ物に気を付けて帰りましょう。自分へのご褒美も忘れずに!
LECやTACなどの予備校各社から、すぐに解答速報が出されますが、50問一度に発表されるわけではなありません。
少しずつ発表されます。
おそらく、受験者から問題用紙を受け取って、一斉に解答を作成するのでしょうね。
結局、すべての解答が揃ったのは、夕方17~18時頃であったと思います。
今年は、難問・奇問が多かったようなので、さらに時間が掛かったのかもしれません。
私は、帰り際の時点で発表されてきた解答を見て、自己採点しましたが、解答に悩んだ問題がある程度合っていたため、試験のことはスッパリ忘れて、ケーキを食べたり、サウナに行ったりして、この世の春を謳歌しました(^^♪
帰宅後に、改めて採点したところ、41点/50点取れており、一応、合格ラインは突破できました。
その後、12/1に、オンラインで合格発表があります。
合否確認には受験番号が必要ですので、受験表は、きちんと取っておきましょう。
合格証は、その数日後に郵送されてきます。
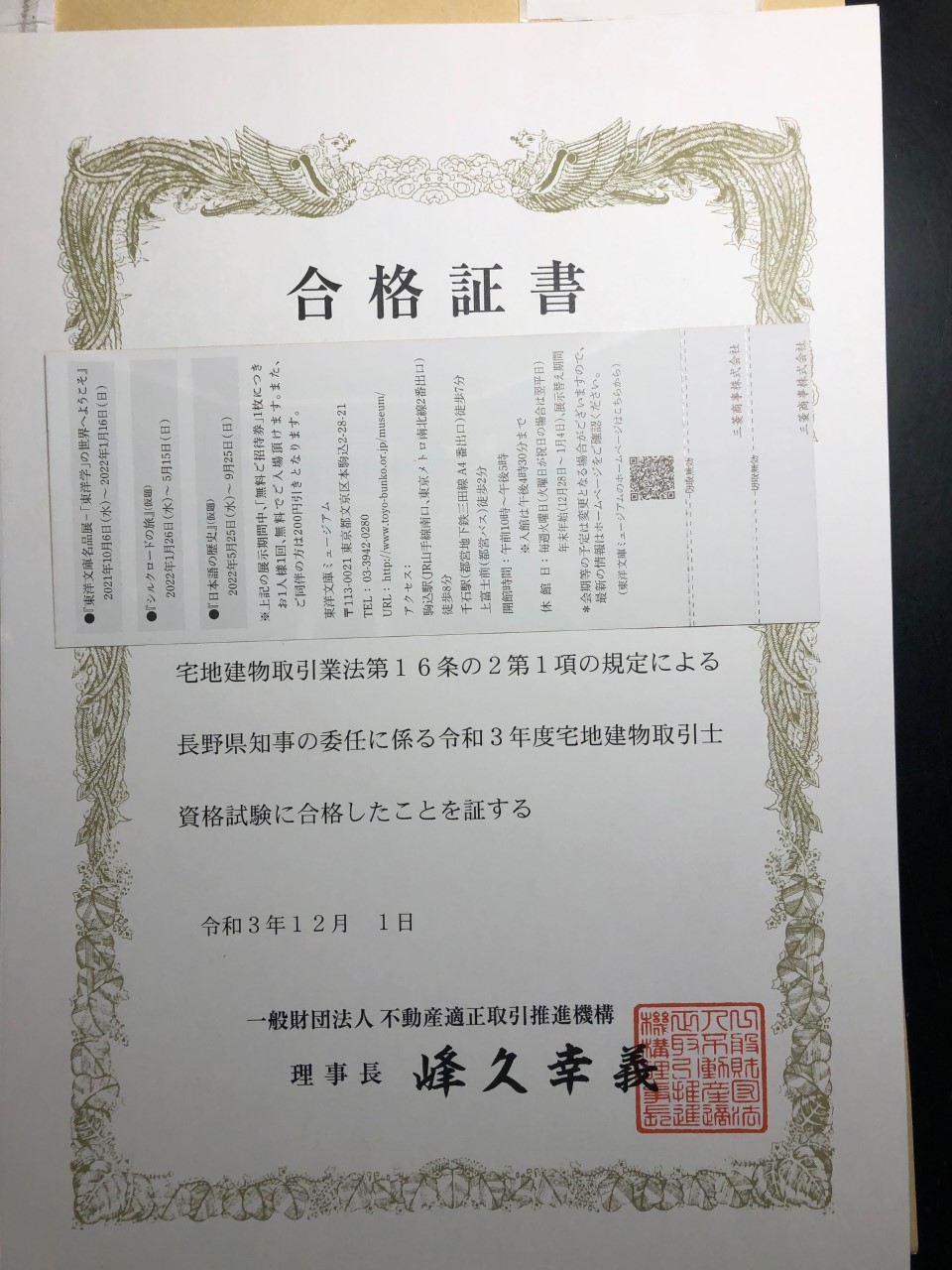
試験が終わって
とにかく、解放感が凄かったです。
やはり直前期は、平日も休日も試験のことが頭を離れず、色々ストレスを感じていたのすが、もう気にする必要はありません。
勉強に使っていた時間がまるまる空くことになりますから、その分、「試験が終わったらしよう」と決めていたことにエネルギーを傾けました。
部屋の整理、資料の処分、ゆっくり睡眠、メルカリ出品、ブログ…、何でも気兼ねせずにできるというのは、素晴らしいですね。
一方、試験は水物ですから、「もし、合格点に達していなくても、やりたいことはやる」と決めておくことも大切でしょう。
うまく行かなかった場合、後悔などから、すぐに来年度に向けての勉強を始めたい気持ちになるかもしれませんが、まずは休んで、リフレッシュする方が大切な気がします(ただし、当日の緊張感や自分の感覚、ミスをした要因などを振り返っておくことは有用)。
一方、せっかく身に付いた学習習慣や、時間の効率的な使い方を放棄するのはもったいないので、それは、今後も維持したいと思いました。
特に、今回の宅建試験を通して、Youtubeの有用性に気付けた点は大きかったです。
色々な方の有料級の講義が、無料で聞けるというのは、非常に魅力的であり、学習の幅を広げてくれた気がします。
私は、「Youtube premium」という有料プラン(月額1500円ほど)に加入したのですが、これも、非常に優良でした。
これは、途中広告が出ない、バックグラウンド再生(スマホの画面を閉じても、音声が流れる)やオフライン再生ができるといった機能があり、通勤中などの耳学問に使えるため、電波環境があまりよくない私には、ぴったりでした。
パソコンの前などで、改まって勉強する時間も必要ですが、「ながら学習」も大切です。
私はよく、ジムでトレーニングしながら、聞いていました(分からない問題が出ると、ダンベル運動が止まるので、他の方からは、さぞ変に見えたことと思います(;^_^A)
今では、FPや英語など、最近、興味がある分野の動画を少しずつ見ています。
こうやって、学習経験によって得た気付きが、次につながっていくのも、よいですね。
また、「試験勉強をしなければ」という制約を設けることによって、「実は、自分がやりたかったこと」が見えてくるのも、良かったです。
実は、マンション管理士や行政書士など、次のステップについても、一応は検討したのですが、今は、副業やセミリタイア後の収入などについて考えたいと思ったので、見送りました。
日々の生活の中で使える時間は限られていますので、優先順位を考えて、メリハリを付けたいものです。
終わりに
こうして、私の宅建受験への道は終わりました。
運よく「合格」を手にすることができ、また、上記のとおり、様々な気付きも得られましたが、反省点もあります。
それは、「セミリタイアしたい」という目下の大目標に対して、具体的には結び付いていないことです。
今のところ、宅建士になるわけでもありませんし、不動産業界への転職を希望しているわけでもありません。
また、合格しても、給与は上がりませんし、副業として、何か始められるわけでもありません。
ひょっとしたら、いざという時のセーフティネット(再就職しやすいなど)になったり、ライティングの強みにつながったりするかもしれませんが、今のところは、「完全に趣味」です(ブログのネタにできたのは、唯一よかった)。
振り返ってみると、私は、これまで幾つか資格を取得しましたが(秘書検定、色彩検定、FP、漢検など)、それらが何かに結びつくことはなかった気がします。
単に「頑張っている感覚を得たい」とか、「自信を付けたい」といった思いが先行して、無駄なことにエネルギーを注ぎがちだなと感じました(努力病、向上心のワナ)。
今回の受験で、改めて、そうした点に気付けましたので、今後は、人生の目標や進みたい方向性をしっかりと見極めてから、行動したいと思います。
また、学習方法の工夫や根気よく続ける力は、だいぶ身に付いてきた気がするので、自分の強みとして、うまく成果に結び付く形で、使っていきたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
学習中の皆様、受験を考えている皆様、一緒に頑張りましょう(o^―^o)