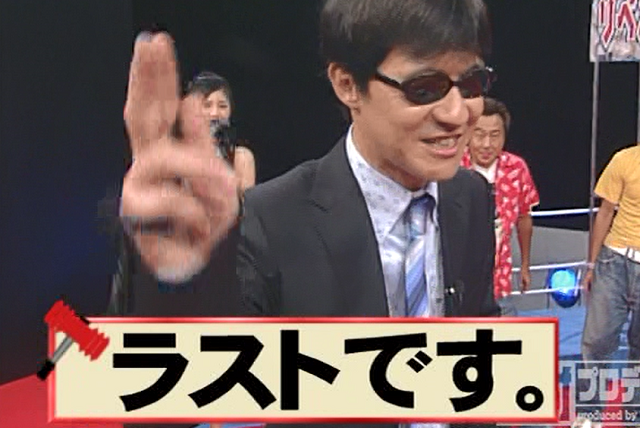こんにちは、うさうさです。
来たる12/19には、2021年度の宅建試験第2回が実施されますね。
私は、運よく1回目(10/17)で合格することができましたが、これから受験される方の参考になるかもしれないので、体験記をまとめます。
受験を検討される方の参考になれば幸いです。
なぜ宅建を受けるのか。
①民法など基本的な法律関係が学べ、仕事に直結する
②勤務中に勉強していても、「仕事の延長」で済む(私の場合)
③国家資格であり、自信になる。FIREした場合の支えになる。
(ココナラなどで仕事を探す際にも、一定の優位性があるのでは?と感じた。)
④合格すれば、資格は一生有効
⑤不動産関係の基礎知識が身に付く
特に大きいのは、②でしょうか。
令和3年(2021)は、現部署での勤務も3年目になり、仕事に余裕が出てきたため、スキマ時間がかなりあると思ったのです。
そんな中、「ぼんやりと座っているのはもったいない!
でも、好き勝手をするわけにはいかない(在宅勤務時はよかったです。懐かしい…)。」という制約がある中で、人的資本を高める一手段になるのではと考えました。
また、民法などの基礎的な法律知識は、日本で生きていく上では、持っていた方が断然有利です。
様々な契約行為(例えば、家の賃貸)は、日常的に行われていますし、不動産、相続などの知識は、どこかで必要になるものです。
日々の本業にも、きっと、プラスになるだろうと思いました。
宅建試験とは何か
国家資格であり、独占業務(有資格者以外、業務を行うことができない種類の仕事)があります。
合格率は20%台と低めですが、簿記のように、年度ごとに難易度が著しく上下することはなく、基礎知識を問う問題が中心のため、学習を続けていけば、合格自体はそれほど困難ではありません。
受験資格に制限がないという点も魅力で、受験者数(2021年度は、受験申込者約25万人、受験者約21万人)も多い、人気資格です🌟
また、マンション管理士、社労士、行政書士、司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士などの上位資格へとステップアップしやすく、足掛かりとして受験される方も多いみたいですね。
法律系資格の登竜門的な位置づけです。
試験は、毎年10月、マークシート式の問題が50問出題されます(2020年以降、12月も実施されており、年2回となっています。)。
試験範囲は、大きく3つに分かれています。
①権利関係(民法、借地借家法)
②法令上の制限(建築時の制限+税、その他)
③宅建業法
このうち、出題数は、③>②>①の順に多く、逆に、難易度は、①>②>③の順となります。
つまり、比較的優しい問題(単純知識を問う問題)の配点が多いため、取り組みやすい試験と言えるでしょう。
合格までのアウトライン
受験に当たって、最初に考えたのは、「とにかくお金は掛けたくない!」でした。
私は、2021年3月から勉強を始めましたが、受験の決め手となったのは、ネット上の無料講座の存在です。
簿記は、リベ大で勧めている「クレアール」の有料講座を利用したのですが、動画やテキストが私には合わず、かなりの労力を要しました(そもそも向いていなかった可能性もありますが…>_<)。
宅建については、オンラインで無料動画配信を行っている「タキザワ予備校」というものがあることが分かりました。
口コミ評価も高く、メールアドレスを登録するだけで、基本講座をすべて無料で視聴できるというものです。
他の有料講座は、安くても4万円以上する中、「そんなうまい話があるのだろうか?」と疑いましたが、試しに動画だけでも視聴したところ、講師の説明がかなり分かりやすい!
クレアールで懲りていた私は、これにビビッと来ました。
しかも、動画だけでなく、テキストも無料とのこと!
実際は、「解説動画にテキストの一部が映るため、それを参照せよ(欲しい人は、有料で注文可能だが、それもかなり安い。ちなみに、私は、市販のLEC解説本を購入しました。恩知らず…💦)」という形なのですが、はじめは、それで充分と思いました。
「行動は早く、初期投資は少なめに」というのは、投資の鉄則ですもんね!
また、2時間×24講座となっているのですが、1動画は、長くても15分程度。
スキマ時間での学習がしやすい点もいいなと思いました。
全体の分量やゴールがあらかじめ分かるってこと、意外と大切ですよね。
途中で、モチベーションが下がったり、先が見えないと、不安になったりしますから。
以後、「とりあえずやってみるか。」「勉強したことは無駄にならないし。」と、軽い気持ちで動画視聴を続け、3月中に、①権利関係を一通り終えることができ、6割ほどは理解できたため、本格的な受験を決めました。
そして、4月中に、②法令上の制限、5月のGWころまでに、③宅建業法の動画を一通り見終えて、一応は、試験範囲を網羅した形となりました。
実際のところ、フルタイムで仕事をしながら、このペースで進めるのは、かなりキツく、一応、目標期限を決めて、平日は最低1単元を視聴し、土日は、まとめて一気に視聴する形で、何とかたどり着いた形です。
もちろん、「初めから全て理解できた」ということはなく、「ふーん、そんな話がテストに出るんだ。」くらいの感覚でした。
しかし、分野によっては、紛らわしい論点(例えば、①権利関係の「造作買取請求権」と、「建物買取請求権」など)も多いので、忘れないうちに、一気に取り組んだ方がよい点もありました。
また、「一通り試験範囲を終える」ということは、敵の全容を把握するということですから、安心感につながります。
※宅建試験は、フリーザ様のように、何段階も変身するということはありません。
あと、一番初めに、宅建試験のマンガ本を読んで、何となく全容を理解していたことも大きかったように思います。
例年、法改正があるので、最新版の方がよいですが、流れをつかむ目的であれば、古本屋やメルカリなどで、過去の年度版を探してみてもよいと思います。
私は節約のため、そうしました。運よく、2017年度版のものを100円で購入。
特に、②法令上の制限など、行政関係は、細かい表が多数出てきますので、無防備に飛び込むと、心が折れてしまう恐れがあります。
入り口のハードルは、極力、下げておくことは非常に大切です。
オススメの学習方法
まずは、私の使った参考書、教材、動画をご紹介します。
テキスト
LEC出る順宅建士 合格テキスト(②法令上の制限、③宅建業法のみ)
LEC出る順宅建士 当たる!直前予想模試(①~③すべて)
LEC出る順宅建士 一問一答〇×1000肢問題集
U-CANの宅建士まんが入門(古本屋で2017年度版のものを購入)
※合格後、宅建士として働きたい方は、テキストを取っておいた方が良いそうです。
「ここまで業務に関連する知識がまとまった本は、開業後もないから」という話を、何かの動画で聞きました。私は、迷わずメルカリで売りましたけどね^^;
動画(いずれも無料+どの先生も、説明上手)
タキザワ予備校(メールアドレス登録後、無料視聴可能 http://takken-school.net/)
ゆーき大学(youtube動画。https://yuki-unv.com/)
棚田行政書士の不動産大学(youtube動画。http://tanadaregal.seesaa.net/)
学習方法
とにかく、一通り論点を学んだあとは、過去問を繰り返し解くことに尽きます。
というのは、宅建は、ひねった問題が少なく、過去問の焼き直しが多いからです。
実際、過去問集を見ると、同じような表現の選択肢が何度も出されています。
つまり、出題されるポイントが絞られているということです。
前述のとおり、②法令上の制限で学習する、「都市計画法」や「建築基準法」は、細かい規定が多く、市販の参考書を見ると、吐き気がしてくる内容ばかりです。
しかし、実際に出題されるポイントは絞られていますから、その部分だけ覚えれば、問題自体は解けます。ここが、司法書士などの上位資格との大きな違いですね。明らかに難易度が違います。
そして、タキザワ予備校の動画は、必要部分に絞った作りになっており、解説も、出題される点を中心に補足してくださるので、非常に優良でした。
私は、①権利関係は、タキザワ予備校の動画を見ながら、ノートにまとめ、②法令上の制限と③宅建業法は、LECのテキストを使ったのですが、余白部分に書き込んだ、講師のコメントが、後に過去問を解く際、大変役に立ちました。
やはり、専門家の知恵・経験ってすごいですね。
また、ゆーき大学のゆーき先生は、youtubeで宅建受験の動画を展開されているのですが、こちらは、更に要点を絞って解説されており、非常に参考になります。
医療では、「セカンドオピニオン」という言葉がありますが、同じ内容について、異なる解説を聞くことは、理解を深めてくれます。
特に、②法令上の制限については、イメージしにくい用語(例えば、「用途地域」、「特別用途地域」、「特定用途制限地区」など。未だに、日本語とは思えない…( ´艸`))が多い中、ゆーき先生の動画は、行政機関HPなどの引用画像を貼ってくれていたりして、非常にイメージが掴みやすかったです。
動画でもおっしゃってますが、「イメージを作る」というのは、応用問題を解く上で、非常に重要ですね。
大学受験などでも、「自分に合った参考書を探せ」、「分からなければ、他にいい参考書を探せ」「よい参考書が見つかれば、とにかく、それを繰り返せ」と言われますが、今は動画で、しかも無料で見られるのですから、いい時代になりました。
ほかにも、よい講座があるかもしれませんので、理解しにくい単元は、色々な解説動画を探してみるとよいと思います。
前述のとおり、記述や図表が多いため、②法令上の制限と③宅建業法は、LECの参考書と過去問を購入しました。
ところが、タキザワ予備校の資料に比べると、LECの読みにくいこと!
本だけで、独学合格された方は、本当にすごいと思います🌟
LECの参考書を基に、独学を始めていたら、挫折していた自信があります。
もちろん、LECの方は、出題率の低い情報も載っているため、合格レベルに達するのに必要な知識がまとめられているのでしょうけれど、初学者は、敷居の高さを感じて、挫けてしまう可能性が高いと思います。
ただし、令和3年の試験では、LECの本にも載っていないような問題が出ました。
試験対策が意味をなさない問題もあるのです(;^―^A)
上記youtuberの先生方によると、「皆、youtube動画で勉強するようになって、平均点が底上げされたため、難化傾向にある」とのこと。
早めに受けておかないと、インフレしそうですね。おそろしや。
とはいえ、基礎なくして応用は解けませんから、まずは、アウトラインや基礎の基礎をたたき込んだ上で、脇の知識を広げていく方が良いと思います。
せっかく過去問に取り組んでも、全く分からないのでは、やる気が出ませんもんね。
前編の終わりに
いかがでしたでしょうか。
資格試験は、比較的長丁場になるので、目的意識をはっきりさせておいた方が、途中で挫けてしまう確率は下がると思います。
私の場合、それほど明確な目標もなく、また、給与UPなどのインセンティブもありませんでしたが、試験勉強を通じて得られる知識は、きっと、今後の資産運用に生かせると思いました。
また、(何かとグレーな噂の多い)不動産業界の内情を知れるのでは?との期待もありました。
長くなってきたので、前編はここまでとします。
中編は、過去問を解くペースや、試験本番までに行った学習スケジュールを中心に、まとめたいと思います。
引き続き、ご覧いただけましたら幸いです。